
家事や子育てを抱える多くの主婦の方は、正社員ではなく派遣やパートの仕事を探すことも多いかと思います。「できれば融通の利く仕事がしたい!」と考えていませんか?主婦の方の勤務体系としては派遣とパートはどっちがいいのでしょうか。このページでは、派遣とパートの違いだけでなく、「103万円の壁」が「150万円の壁」へと変更になった「扶養控除制度」についても解説します。
主婦の方が派遣という働き方を選んだ理由(体験談あり)
-
働く皆さまをアデコの担当者がサポート!ブランクがあってご不安な方も安心してご就業いただけます。
このような担当者のサポートは派遣社員として働く場合の大きなメリットです。
主婦が働くためにクリアしたい条件
毎日の家事や育児などもこなさなくてはならない主婦が働くにあたって、職場に求める条件が複数あるという人も多いはず。主婦が長期的に無理せず働ける職場を見つけるためには、次のようなポイントを重視して仕事探しをしてみるといいでしょう。
- 通勤時間が短い
- 就業時間の融通が利く
- 早出や残業がない
- 急な欠勤にも対応してもらえる
- 子育てへの理解がある
- ブランクがあっても働きやすい
ほかにも、過去の経験を生かせる業務内容であることや、体力面に負担のない仕事であることも大切ですね。
派遣とパートの違いとは?
雇用形態 |
就業期間 |
社会保険・雇用保険 |
賞与 |
退職金 |
交通費 |
転勤 |
研修制度 |
派遣会社のフォロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派遣 | 有期 | 原則あり | 時給に含む | 時給に含む | 有 | 無 | 有 | 有 |
| アルバイト・パート | 案件により | 案件により | 案件により | 案件により | 案件により | 案件により | 案件により | 無 |
ここからは、雇用契約や契約期間、働きやすさなどが、派遣とパートではどのように違うのかについてご紹介します。職場に求める希望と照らし合わせて、どちらが自分に合っているのかを考えてみましょう。
雇用契約
パートの場合は、自分で直接、勤務先となる企業へ応募し、選考を受けることとなります。雇用契約も、勤務先となる企業と個人とで直接結びます。
一方、派遣の場合は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先である企業から指揮命令を受けて働くことになります。
つまり、パートの雇用主は実際に働く企業である一方、派遣社員の雇用主は派遣会社になるのです。そのため、派遣社員の給料は派遣元である派遣会社から支払われます。雇用条件についての相談も、勤務先の上司にではなく、派遣会社の担当者に行います。
契約期間
雇用期間は、パートは特に決められていないことが多いため、任期満了を気にせずに働くことができるのも派遣との大きな違いといえるでしょう。一方、派遣社員は有期契約のため、定期的な契約更新が必要となります。同一の組織単位で就業可能な期間は最長で3年です。しかし、例外もあり、派遣元に無期雇用されているという場合や60歳以上の場合は3年を超えて働くこともできます。労働者派遣の期間制限について詳しくは下記ページでも解説しています。詳しくはこちらをご確認ください。
労働者派遣の期間制限について
また、有期雇用契約の更新が複数回行われ、その期間が通算5年を超えている場合、無期雇用派遣に変更することで期間の制限を超えて働くことができます。無期労働契約への転換ルールについては下記ページで詳しく解説しています。詳しくはこちらをご覧ください。
無期労働契約への転換ルールについてはこちら
なお、派遣の仕事は、勤務先から契約期間を更新しない通達を受けることもあれば、自分都合で更新しないという選択も可能です。
仕事の評価制度
パートの場合、原則として直属の上司が仕事の評価やフィードバックを行います。業務成績などに応じて、時給アップなどが迅速に反映されるというメリットがあります。
派遣社員の場合は通常、派遣先企業の評価をもとに派遣会社経由でフィードバックされます。評価とともに、派遣社員が就業先でより活躍できるよう派遣会社からのサポートも受けることができるので、よりキャリア形成につながるでしょう。
また派遣会社が実施する研修制度や、キャリアコンサルティングを活用できるのも派遣社員の大きなメリットです。就業中の方は無料、もしくは特別価格で受けられるサービスも多数あり、キャリア開発も効率的に行えます。
アデコでも、豊富なキャリアサポートを取り揃えております。詳しくは下記ページからご確認ください。
拘束時間の自由度
勤務時間や休日、残業の有無については、パートと派遣どちらも選択可能であることがほとんどです。しかし、派遣社員の場合、最近では「週3日」といった求人も増えていますが、一般的には正社員と同様フルタイムもしくはフルタイムに近い勤務が条件となる場合もあります。小さな子供がいる主婦は、子供の預け先について考えなくてはならない可能性もあります。
勤務時間の自由度としては、「パート>派遣>正社員」と考えたほうが良いでしょう。
福利厚生の充実度
派遣社員は、派遣会社の社会保険や福利厚生を使うことができます。また、派遣はパートよりも時給が高めの仕事が多い傾向があります。派遣であれば、一定の条件を満たす方であれば派遣会社が年末調整を代行してくれるというのも大きなメリットです。パートの場合、確定申告を自分でしなくてはならないことがあります。
アデコでも、派遣会社の皆さまに安心して就業いただけるよう、サポート体制を整えております。旅行やレジャーの割引が受けられる福利厚生サービスや育児とお仕事の両立をできるような育児支援サービス、その他にも結婚祝い金(5万円)・出産祝い金(5万円)などアデコならではのサポートが多数。詳しくは下記ページからご確認ください。

急なお休みに対応しやすいのはどっち?
主婦が働くとなると、子供が体調を崩してしまったときや突然予定が入ってしまったときなど、急遽休みを取らなくてはならないことも考えられます。派遣とパートでは、休みに関する融通が利きやすいのはどちらになるのでしょうか?
先ほどもご紹介したように、就業時間に関して派遣社員は正社員に次いで拘束が強いことがあります。そのため、急な休みを取得することが難しかったり、評価が下がる原因になってしまったりというケースも。パートの場合は面接の時点で、子供がいるため休みを柔軟に取りたいといった希望を伝えることができます。家庭の事情も理解し、柔軟に対応してくれやすいのはパートといえるでしょう。
扶養内で働くかどうかも鍵になる
主婦の場合、夫の扶養に入っているという人も少なくないと思います。そこで確認しておきたいのが、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」といった扶養控除制度です。
かつては103万円の壁と呼ばれていたように、主婦の年収が103万円を超えてしまうと税金が高くなってしまいました。しかし、2018年1月からは150万円の壁へと変更になりました。ここでは、この主婦が働く場合の「年収の壁」に関して、知っておくべきことを確認していきましょう。
- ※ここでは夫と配偶者(主婦)を想定して解説しますが、主夫とその配偶者にも読み替えることができます。
| ご本人の年収 | ご本人への課税の有無 | ご本人の社会保険料負担 | 配偶者の所得への控除の有無 | |
| 住民税 | 所得税 | |||
| 100万円以下 | 非課税※1 | 非課税 | 不要 | 対象※2 |
| 100万円超~103万円以下 | 課税 | 非課税 | 不要 | 対象※2 |
| 103万円超~106万円未満 | 課税 | 課税 | 不要 | 対象※2 |
| 106万円以上~130万円未満 | 課税 | 課税 | 条件により発生※3 | 対象※2 |
| 130万円以上~150万円以下 | 課税 | 課税 | 発生 | 対象※2 |
| 150万円超 | 課税 | 課税 | 発生 | 対象外 |
2017年までの「103万円の壁」とは?
扶養に加入している主婦の年収が103万円以下であれば、そこからすべての人が受けられる控除である「給与所得控除の55万円」と、「基礎控除の48万円」を差し引き、課税対象所得(税金のかかる所得)をゼロにすることができ、主婦の給与に対して所得税は発生しません。
また、主婦の年収が103万円以下の場合、夫は「配偶者控除」として一律38万円の所得控除を受けることができます。
「150万円の壁」とは?
103万円を超えると、主婦自身に所得税が発生し、配偶者控除を受けられなくなる場合があります。しかし特定の条件を満たせば、150万円までなら控除が適用されます。これが「配偶者特別控除」で、この上限金額の150万円がいわゆる「150万円の壁」です。
「配偶者特別控除」の要件を満たすことで、前述の「配偶者所得控除」と同じ38万円の所得控除を受けられます。主婦の年収が150万円以下で、かつ夫の合計所得金額が900万円(年収1,120万円)以下であれば夫の所得から配偶者控除として一律38万円を差し引くことができます。上限を超えると、控除額は38万円から段階的に減額されます。
配偶者特別控除を受けるための要件についての詳細は以下の国税庁のHPをご確認ください。
国税庁のホームページはこちら「150万円を目指せる?!」 社会保険の「106万円の壁」も確認!
配偶者特別控除を受けることで、103万円の壁を超えて、150万円までは控除額が変わりません。あくまで配偶者である夫の所得控除に関する話ですので、主婦自身の税金はかかりますが、「年収150万円を目指せる!」と思われる人も中にはいるかと思います。しかし、ここで確認したいのが社会保険制度です。
年収106万円以上(賃金の月額が8.8万円以上)かつ、勤務時間が週20時間以上30時間未満、2ヶ月を超えて勤務する見通しがある、従業員が101人以上の会社で働いている条件を満たす主婦は、夫の扶養から外れて社会保険料を自分で負担する必要があります。
社会保険料を負担することで、国民年金に比べて将来受け取る年金が増えます。しかし、負担金額が増えることで加入前と比べて手取りが少なくなってしまう場合もあるため、場合によっては労働時間などの調整をしたいという方もいるかもしれません。また、夫が厚生年金に加入している場合は、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)となるため、国民年金を支払ったことと同じ扱いとなります。
派遣はパートと比較して時給が高く、週数日の勤務でも予想以上の年収となることもあるため、扶養内で働きたい場合には、働き方も就業先も慎重に決める必要があるでしょう。
Point.2024年10月以降は社会保険の加入条件がさらに拡大されます
現在は101人以上の会社規模の場合は社会保険に加入する必要がありますが、2024年10月以降は51人以上に変更されます。これにより、従業員数が少ない企業で働いていても、社会保険適用条件に当てはまることもあります。
アデコは上記加入基準を満たした派遣社員の方は、社会保険と雇用保険に加入していただいています。
今後の働き方も見据えた選択をしよう
派遣とパートの違いについて、主婦が働くにあたっての視点からご紹介してきました。
継続して長期的に働きたいのか、いつか辞める予定があるのかなど、今後の働き方についても考えたうえで、自分の希望する条件に合った働き方を判断することが大切です。夫の扶養に加入している場合は、配偶者控除や社会保険に関する「年収の壁」についても確認しながら、仕事と家庭とのバランスを考えていきましょう。
※この記事は、2023年10月に更新された記事となります。
アデコで人気の求人特集
関連記事
あなたの経験や希望に合ったお仕事情報をご紹介
ご登録はWeb上で完了します(来社不要)。また、ご希望条件や職歴等はインタビュー(電話面談)でお伺いします。
お仕事開始までの流れ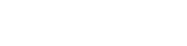












前職の友人が「アデコはサポートが良い」と言っていたことを思い出して登録しました。仕事を始めて間もないころには、子供が体調を崩して、一時は仕事を続けられるかどうか不安になりましたが、就業先の上司・同僚やアデコの担当者から力強いサポートをいただき、続けることができました。今後も今のように育児と仕事のバランスをとりながら両立させていきたいと思います。