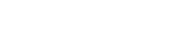職場では、思いも寄らなかった事態やトラブルが起こるものです。想定外の事態が起こると、時には業務中に感情的になってしまうこともあるでしょう。そんな時に有用なのが、アンガーマネジメントです。
アンガーマネジメントは、「怒り」の感情を理解することで上手にコントロールする方法です。アンガーマネジメントを身に付けることにより、一時の感情に流されず、冷静に状況をコントロールできるようになります。
本記事では、アンガーマネジメントの基本的な考え方や、具体的な手法を解説していきます。
人事用語に関するお役立ち情報をお送りいたします。
メールマガジン登録
アンガーマネジメントとは?
アンガーマネジメントは、1970年代にアメリカで提唱・開発された、怒りをコントロールするための手法です。
人間の持つ自然な感情の1つである「怒り」と、上手に向き合っていくために研究されました。怒りについて理解し、取り組むことで良好な人間関係の維持や、職場でのチームワーク・生産性向上が期待できます。
アンガーマネジメントの意味
アンガーマネジメントとは、怒りの感情と付き合っていくためのトレーニングのことをいいます。ただ怒らないのではなく「怒る必要のない出来事には怒らない」ことが目的です。
アンガーマネジメントというと絶対に怒らないことをイメージする人もいますが、まったく怒らないということではありません。
企業がアンガーマネジメントに注目する背景
アンガーマネジメントが注目されるのには、企業における生産性や競争力に好影響を与える背景があります。具体的にその理由を見ていきましょう。
ダイバーシティの浸透
ダイバーシティという概念に代表されるように、人間の価値観は年々多様化しています。企業においてさまざまな考えを持つメンバーが集まり業務を遂行するケースは増えつつあり、価値観の相違によるいさかいを避けるためにも、アンガーマネジメントは有用といえるでしょう。
あわせて読みたい
ダイバーシティとは? 基礎知識から働き方改革、施策例をわかりやすく解説
この記事では、ビジネスにおけるダイバーシティの基礎知識から活用方法、人事施策などをわかりやすく解説していきます。
職場におけるパワーハラスメント防止
パワーハラスメントは、受けた当人のダメージが大きいだけではありません。ハラスメントがあるという事実だけで組織のモチベーションを大きく損なってしまうでしょう。アンガーマネジメントを学び、適切な対応方法を身に付けることでパワーハラスメントの予防にもつながります。
あわせて読みたい
企業が行うべきハラスメント対策の重要性とは? 具体的な事例を交え紹介
ハラスメント対策の重要性や事例などについて、詳しく紹介していきます。
生産性やチームワーク向上
怒っている時間は、問題の前向きな解決策などが考えられず、生産性がある状態とはいえません。パワーハラスメントの防止という観点だけでなく、適切なコミュニケーションを心掛けることで職場の人間関係が良好となり、結果的に生産性やチームワークの向上が期待できます。
アンガーマネジメントを実践するメリットと効果

アンガーマネジメントを実践するメリットと効果にはどのようなものがあるのでしょうか。 怒りをコントロールすることで、自分だけでなく周囲にも好影響があります。
怒りをコントロールできる可能性がある
アンガーマネジメントを実践する過程において、怒りのメカニズムや、自分の怒りのパターンを理解することで、怒りをコントロールできるようになります。
怒りを感じて衝動的な言動をとってしまうのは、自分にもチームにも良い影響を与えません。衝動的に発言してしまうことで、周囲からの不信感や信頼の喪失につながってしまうこともあります。
また怒りを抑えきれない自分に対してネガティブに感じ、自己肯定感を低下させてしまうこともあるでしょう。
適切な叱り方を身に付けられる
パワーハラスメントを恐れるあまり、「部下をうまく叱れない」という管理職の悩みもあります。しかし、指導するべき時に正しい振る舞いができないのでは、リーダーやマネージャー、管理職としての職務を果たせません。
部下をうまく導くために、アンガーマネジメントを通じて「適切に叱る」というスキルを学ぶことはマネジメントにも役立ちます。
怒る回数を減らし、ストレスも減らせる
怒りを抱えることは、当事者にとってストレスとなる場合があります。
アンガーマネジメントにより、怒りをコントロールすることで悩む頻度を減らし、自分のメンタルヘルスも保ちやすくなるでしょう。
視野が広がる
アンガーマネジメントを実践することにより、自分の感情はもちろんのこと、相手の考え方や意見に対して耳を傾ける習慣も身に付きます。結果として、複合的に物事や出来事を考えられるようになり、視野が広がるといえるでしょう。
視野が広がることで新たな気付きを得られる機会も増えます。
チームの生産性が向上する可能性がある
アンガーマネジメントを実践することで、コミュニケーションが取りやすくなり、業務も円滑に進められます。職場の雰囲気も良くなり、意見を言いやすく働きやすい環境ができることで、生産性向上につながるでしょう。
怒りのメカニズムや種類を理解する
アンガーマネジメントの実践には、怒りのメカニズムや性質の理解が欠かせません。「怒り」という感情の性質や特徴を見ていきましょう。
怒りを感じるメカニズム
怒りは、先の見えない不安やマイナス感情、状態が続くと発生しやすくなります。
怒りはある出来事に対して、自分自身が意味付けをすることによって生まれます。自分がなぜ怒りを感じるのか、怒りに隠れているほかの感情に気付くことで、怒りのパターンを理解することが可能です。
怒りの種類を理解する
怒りは大きく4つに分類されるといわれています。それぞれの種類や特徴を知っておきましょう。
| 強度が高い | 強度が高い怒りは、声を荒げたりするなどの言動につながりやすい衝動的な怒りです。抑えるのが難しいため、怒りを溜めないように意識することが重要です。 |
|---|---|
| 持続性がある | 時間が経っても忘れられない怒りや、思い出していらいらしてしまう怒りが「持続性がある怒り」です。「あの時ああすれば良かった」と消化できない怒りや後悔があるため、持続してしまう状態です。 |
| 頻度が高い | 例えば、メンタルヘルスが良くない状態では、些細なことでも刺激となり怒る頻度が多くなることもあります。精神的な疲労が蓄積し、悪循環に陥りやすい状態です。 |
| 攻撃性がある | 相手を攻めるあまり、攻撃してしまうタイプの怒りです。対象は相手であったり物であったりさまざまですが、周囲にも悪影響を与えます。 |
アンガーマネジメントの具体的な手法
アンガーマネジメントの具体的な手法にはどのようなものがあるのでしょうか? 1つずつ詳しく見ていきましょう。
- 16秒ルール
-
怒りを感じてから、冷静に考えられるようになるまで一般的に6秒かかるといわれています。例えば、かっとなってしまっても6秒抑えられれば冷静な思考を取り戻せるということです。
6秒待つことを忘れてしまう場合は、1からではなく6からカウントダウンするなど、意識的にタスクとして自分に課すことで、6秒ルールを実施しやすくなるといえるでしょう。 - 2思考を止める
-
怒りを感じた時に、一度思考を止めるのも有効です。例えば、怒りを感じる文書やメールを見てしまった時に、一時的にファイルや画面全体を閉じることで思考を止めやすくなります。意識的に思考を止められると、怒りに任せた言動を抑制する効果があるといえるでしょう。
- 3深呼吸をする
-
怒りを感じた時は、深呼吸をしてみましょう。深呼吸をすると、副交感神経が優位になるため、落ち着きや冷静さを取り戻すことができます。4~5秒かけて息を吸い、10秒程度かけて吐くことを意識してみましょう。
- 4アンガーログで怒りのパターンを見つける
-
アンガーログとは、その名のとおり、怒りについて記録したものを指します。怒りを感じた日時や場所、程度を記録することで、自分が怒りやすい状況などのパターンを見つけられます。
パターンを把握することで、自分の怒りの感情を認識し、対応がしやすくなるといえるでしょう。 - 5怒りを数値化してみる
-
アンガーログを記録する時や、怒りを感じた際に、その怒りを数値化することも客観的に自分を見つめることにつながります。数値化することで、自分の怒りの傾向がより理解できます。
- 6怒りを相手へのリクエストに置き換える
-
怒りの感情を抱いた時、不満ではなく相手に「こうして欲しい」という具体的なリクエストの形で伝えるのも有効です。
-
例えば、
- 今でも満足しているが、期日を少し早めてもらえるとより良い
- 帳票の形式を、集計しやすいようにサマリーを入れてもらえるとありがたい
- 最低限〇〇は意識して欲しい
など、リクエスト形式で相手に伝えれば怒りの感情を抑えながら要望を伝えられます。
アンガーマネジメントの実践方法
アンガーマネジメントには、どのような方法があるのでしょうか。日常でも行える具体的な実践方法を紹介します。
自分の怒りを理解する
自分の中にどのようなネガティブな感情があるのかを書き出し、整理しましょう。そうすることで心理的に安心し、怒りを上手に扱えるようになります。まずは自分の中にある怒りに向き合ってみましょう。
ネガティブな感情を溜めない
ネガティブな感情を溜めないためには、趣味を満喫したり外に出かけてみたりすると効果的です。また、リラックスできる音楽を聴いてみても良いでしょう。自分に合う方法を探すことが大切です。
怒りを数値化してみる
怒りを10段階で数値化してみるのもおすすめです。段階や強さを測り、自分の怒りの度合いを見つめなおすと、客観的な判断ができる可能性があります。
人のリフレッシュ方法を真似してみる
たとえば、テレワークでなかなか外出できずイライラすることがあるかもしれません。そのような時は「昼休憩のうち15分は散歩に出かける」「1時間に一度は軽いストレッチをする」など、ほかの人が実践して効果があったリフレッシュ方法を試すのも有効です。
「べき」の価値観を見直してみる
「~するべき」の気持ちが強いと、それを実行できなかった場合にネガティブな感情が生まれやすくなります。自分の価値観を改めて、可能な限り緩和してみましょう。
まとめ
本記事では、アンガーマネジメントの基本的な考え方から、具体的な実践方法を紹介してきました。
企業経営にもアンガーマネジメントは欠かせない概念であり、生産性やチームワークに影響します。また、職場において良好な人間関係を築いて維持するだけでなく、アンガーマネジメントの実践により自分のメンタルヘルスを守ることもできます。
自分でも実践できる方法として、ネガティブな感情を溜めないことや怒りを数値化することなどが挙げられます。しかし、1人で行うのはなかなか難しいと感じる人もいるかもしれません。
アンガーマネジメントの実践にあたっては、外部サービスの力を借りるのも1つの手です。
アデコでは、総合人材サービス企業ならではの独自EAP(従業員支援プログラム)を提供しています。

アデコのEAP・メンタルヘルスケア
企業の組織・人事・管理監督者・従業員、その家族に対して、さまざまなサービスをご用意しています。
弊社では、上記のような人事関連のキーワードを分かりやすくまとめ、定期的に更新しております。
メールマガジンにご登録いただくと、労働法制や人事トレンドなどの最新お役立ち情報をチェックいただけます。