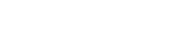働き方の多様化に伴い、外部に業務委託契約をする企業が増えています。しかし、正確にいうと「業務委託契約」という契約はありません。業務委託契約の形としてあるのは「請負契約」と「委任契約」です。
業務委託における2つの契約形態の違いや、業務委託の契約をする際の注意点を理解することで、状況に合った判断ができます。業務委託についての知識を得て、業務の効率アップを図りましょう。
人事用語に関するお役立ち情報をお送りいたします。
メールマガジン登録
業務委託とは
「業務委託」とは、企業が自社の業務の一部、または全ての業務を外部の企業に依頼することです。「委託」とは、業務などを他者に依頼すること全般を指し、アウトソーシングとも呼ばれています。
例えば、業務委託するメリットの1つとして、定型業務などを委託することで、従業員がコア業務に専念できることが挙げられます。
業務委託契約の種類
ここでは、業務委託契約の3つの種類を紹介します。まずは、月毎に定額の報酬を払う契約です。変動がないため収支の予測がしやすくなり、安定性があるでしょう。ただ、受託者からすると報酬に変化がないため、業務に対してのモチベーションが上がらないことが考えられます。
「次は、業務の成果次第で報酬が変動する契約です。受託者の成果が少ない場合、委託者は支出を減らせるというメリットがあります。ただし、成果が大きくなれば報酬も大きくなるため、バランスを探ることが必要です。
最後は、単発の業務を委託する契約です。継続契約とは違うため、委託者は支出をコントロールしやすくなる契約方法です。受託者からしても、単発であるため安定性は低いですが分かりやすい契約でしょう。
「請負」「委任」「準委任」「派遣」との違い
多くのケースでは、業務を委託した企業と受託した企業の間には、「請負契約」か「委任契約」のいずれかが結ばれていると考えられます。(注:実質的に両者の間に指揮監督関係がある場合には、「雇用契約」が締結されていると評価されます。また、契約内容が「請負契約」と「委任契約」の混合形態と評価される場合もあります。)
「請負契約」も「委任契約」も業務を委託する際に結ぶ契約ではあるものの、2つの契約には明らかな違いがあります。それぞれの契約の特徴を詳しく見てみましょう。
「請負契約」は業務の完成品が目的
請負契約とは、業務を完成させることを目的として結ばれる契約です。正確には、「業務を完成させたことによって生まれた成果物を得る」ことを目的としています。業務途中のままになってしまったものや、業務完了したけれど成果が出なかったものには、本来対価は発生しません。
一例として、企業がデザイナーに依頼するパッケージデザイン制作のケースを考えてみましょう。企業とデザイナーは、依頼内容と成果物に対する報酬額、納期などを含めた請負契約を結びます。
デザイナーには、納期までに依頼に沿ったパッケージデザインを納品する義務が生まれます。手を付けたものの完成に至らなければ、契約を履行したことにはなりません。また、完成品が依頼内容通りではなかった場合には、デザイナーは修正作業を行い、依頼に沿う納品を行うことになります。
もう1つ例をあげます。営業代行の請負契約を結んだとしましょう。営業代行の請負契約を結ぶ際には、例えば「売上金の何%かを受託者に報酬として支払う」という契約です。つまり、受託者が営業活動を行ったプロセスがあっても、売り上げがなければ対価は発生しません。
「委任契約」は業務の遂行が目的
一方で委任契約は、業務の遂行を目的としたものです。業務を行いさえすれば、成果物がなくても対価が発生するところが請負契約との大きな違いです。
ここでも、委任契約の具体的なケースを見てみましょう。
例えば、企業が新人教育の研修のため、講師と委任契約を結んだとします。講師は依頼内容に基づき、研修を行わなければなりません。この場合、研修が契約内容通りに行われれば契約は履行されたことになります。研修後に新入社員が期待通りに学んでくれなかったという状況であっても、報酬に影響することはありません。
請負契約の具体例でもあげた営業代行について委任契約が締結されている場合には、営業業務によって売り上げを伸ばせなくても、契約内容通りに営業を行ったのであれば報酬は発生します。
成果が出なくても報酬が発生するのでは、委託側が損失を受けるようなイメージを抱いてしまうかもしれません。しかし、委任契約では、受託者に「善管注意義務」という義務が課されており、業務遂行にあたり、細心の注意を払うことが求められています。
「準委任契約」は「委任契約」よりも対象範囲が広い
委任契約と似た言葉に「準委任契約」があります。委任契約とまとめて「委任」という言葉が使われることもありますが、厳密にいうと意味が異なるので注意しましょう。
委任契約は、契約締結や税務などの法律行為を委託するものであるのに対し、準委任契約は事務処理など、法律行為以外の行為を委託するものです。ビジネスシーンでは、契約形態として準委任契約が締結されることが多くあります。
例えば、システム開発のテスト作業を依頼する場合は具体的な納品物がなく、かつ法律業務ではありません。そのため、準委任契約が締結されることになります。
「派遣」との違いは指揮命令系権があるかどうか
人材派遣と同じように、業務委託でも、委託先に一定期間常駐するケースが考えられます。この場合、業務委託は労働者派遣とどのような違いがあるのでしょうか。
ポイントは「指揮命令ができるか、できないか」です。人材派遣の場合、派遣先企業は労働者に対し、直接的に指揮命令ができます。一方、業務委託の場合は、労働者の管理は受託企業が行うため、直接的な指揮命令はできません。受託企業の指揮命令の下、労働者は業務を遂行することになります。
また、偽装請負とならないように注意しましょう。偽装請負とは、契約は業務委託でありながら指示内容によっては指揮監督関係があり、雇用関係があると評価される恐れがあるものです。
偽装請負は違法であり、労働基準法や労働者派遣法などに違反する恐れがあります。社内にスタッフを常駐させ、直接指示を出しながら業務を進めたい場合は、業務委託ではなく人材派遣の活用がおすすめです。
- 請負
-
- 契約形態
- 請負契約
- 報酬の対象
- 成果物
- 完成責任
- あり
- 業務内容
- 成果物の作成
- 指揮命令権
- なし
- 委任
-
- 契約形態
- 委任契約
- 報酬の対象
- 業務遂行
- 完成責任
- なし
- 業務内容
- 法律業務
- 指揮命令権
- なし
- 準委任
-
- 契約形態
- 準委任契約
- 報酬の対象
- 業務遂行
- 完成責任
- なし
- 業務内容
- 法律業務以外の業務
- 指揮命令権
- なし
- 派遣
-
- 契約形態
- 雇用契約
- 報酬の対象
- 業務遂行
- 完成責任
- なし
- 業務内容
- 依頼された業務内
- 指揮命令権
- あり
あわせて読みたい
アウトソーシングと派遣はどう違う?業務効率化に役立つそれぞれの特性
業務委託を行うメリットや活用法

業務委託を活用し、自社の業務を外部企業に委託することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか?
メリット 1採用や育成コストを抑制できる
業務委託を活用するメリットは、人材獲得に必要な採用コストや、人材の育成コストを抑制できることです。
人手が足りていない業務をカバーするために従業員を雇用するとなると、採用や育成コストがかかります。しかし、業務委託を活用する場合、業務をまるごと委託先に任せることが可能です。委託先を検討する労力やコミュニケーションコストはかかりますが、新たに人材を採用したり育成したりする手間がかかりません。
メリット 2定型業務を効率化し、コア業務に専念できる
事務的作業のような継続的に発生する定型業務を業務委託することで、業務を効率化できるのもメリットです。また、業務委託によって従業員が定型業務から離れることになるため、本来行うべきコア業務に専念しやすくなります。
業務委託をする場合、正しくスムーズに業務を委託するべく、マニュアル作成や打ち合わせなどをする必要があります。引き継ぎ関係の業務で時間が取られるかもしれませんが、いったん業務が回り出せば、進捗状況の確認のような業務は最小限の労力で遂行できるようになるでしょう。
メリット 3自社にはないノウハウやスキルを活用できる
業務委託を利用することで、システム開発やセキュリティ対策など、自社にはない専門スキルやノウハウを活用できます。
例えば、WEBサイトを新たに構築する際、自社のスタッフでは技術が足りず、思うようにプロジェクトが進まないこともあるでしょう。WEB制作会社に構築業務を委託すれば、委託先の企業がもつプロ人材に、専門的な知識や最新の技術を反映させたWEBサイトを制作してもらうことが可能です。
メリット 4繁忙期など局所的な労働力不足を補える
業務委託を活用するメリットとして、年末や年度末といった局所的な繁忙期に、従業員を採用せずとも労働力を補えることが挙げられます。
繁忙期に慌てて人材採用を行っても、理想とする人材が確保できるとは限りません。採用がうまくいかず、繁忙期に十分な人員を確保できなければ、社員の負荷が高まり、従業員満足度の低下や離職などにつながることもあります。
業務委託を活用することで、スムーズに労働力を補える上、繁忙期後も適切な業務量を維持できます。
業務委託契約する際の注意点

業務委託の契約をする際は、目的を明確にした上で、「請負契約」と「委任契約」のどちらを選択するべきかを慎重に考える必要があります。また、業務委託は社員がコアな業務に集中できるための契約であり、業務委託による管理が社員の手を煩わせてはいけません。
契約時に意識したい注意点が多くあるなかで、以下のような点においても事前に考慮しておきましょう。
持ち出し可能な業務を一任する
業務委託は、社内で行っていた業務の一部を切り取って外部に任せることです。あるいは特殊スキルを必要とする、作業スペースの確保ができないなどの理由で、社内では行えない業務を外部に任せることになります。
よって、依頼する業務を行うのに必要なデータが、外部に持ち出してもいいものであることを確認する必要があるでしょう。企業の運営に関わる重要な業務は、業務委託に向きません。業務委託に一任する仕事は持ち出し可能なデータにとどめるなど、情報漏洩に気を付けましょう。
業務の進め方は具体的な指示ができないと知っておく
業務委託の契約に、雇用関係は発生しません。つまり業務を行う従業員の勤務条件や、業務の進め方についての指示は出せないことになります。
業務委託では、受託者がどのように業務を行うのかは、受託者の自由です。請負契約の受託者には、行った業務の成果物を納期までに納品するという義務があるのみ。委託者が効率的と判断する業務の進め方があっても、そのやり方を強要するのはルール違反です。
契約先の相手は慎重に選ぶ
請負契約は、業務の完成によって生まれた成果物を納品することで、契約が履行されたことになります。業務途中であったり、委託した内容に沿わないものであったりした場合は、報酬は発生しません。修正が必要であれば、受託者には修正の対応をする義務があります。
成果物を納品してくれなければ報酬は発生しないとはいえ、予定していた納品物がないのでは業務に支障がでてしまいます。請負契約をする場合には、きちんと納期を守ってくれる受託者と契約することが大切です。業務委託では途中経過を確認できないので、信頼できる相手を選ぶことが重要でしょう。
また、単に納期を守ってもらえればよいというだけではありません。希望に沿った納品物を仕上げ、修正にも迅速に対応してくれる相手選びをしましょう。守秘義務を怠らず、スムーズに業務を行ってくれる相手を選ぶこともポイントです。
従業員のスキルアップにつながらない可能性がある
外部の人に業務を任せてしまうことで、個人のスキルアップや社内のノウハウ蓄積につながらない可能性があります。
業務委託を簡単に終了できず、予想以上に長く業務委託を利用することになる恐れもあるでしょう。
サービスなどの質が低下する可能性がある
自社製品やサービスをよく理解し、必要であれば研修を受けている社員とは異なるため、委託相手によっては提供する内容の質が低下することが考えられます。
内容の質の低下が確認された場合、別の委託先に依頼し直すとなると余計な時間やコストがかかるため、信頼できる委託先に依頼しましょう。
業務委託契約の作成方法
実際に業務委託契約をするにあたっては、契約書の作成が必須です。
主な契約書に記載する主な項目と、収入印紙が必要かどうかについて紹介します。
業務委託契約書の主な項目と概要
契約書には、次のような項目を記載します。
業務の内容
委託する具体的な業務内容や、成果物の詳細を明記します。
委託料
委託先に支払う報酬がいくらになるのか明記します。
契約期間
契約期間が決まっている取引は、その期間をきちんと明記します。
禁止事項
何か禁止事項があれば明記します。その際は可能なかぎり詳細に記載しましょう。
検品や検収の方法
検品や検収のやり方について、何か指定があれば明記します。
知的財産権等の帰属
成果物の知的財産権等がどちらにあるのか明記します。
秘密保持
秘密情報の取り扱い方や範囲を明記します。
業務委託契約書に収入印紙は必要?
収入印紙とは、租税や手数料をはじめ、ほかの収納金徴収のために政府が発行する証票のことをいいます。
業務委託契約書において、収入印紙が必要なのは主に2種類です。
まず、第2号文書で必要です。これは請負に関する契約書のことで、契約書に記載された金額によって収入印紙の金額が変わります。
それから、第7号文書でも必要です。これは、契約期間が3ヶ月以上である継続的な取引の際に用いられる契約書のことをいいます。第7号文書では、契約金額や内容などを問わず4,000円の収入印紙が必要です。
まとめ
業務委託と一言でいっても、業務の完成を目的とする請負、業務の遂行を目的とする委任があります。似たような意味で準委任や派遣などもあるので、違いをしっかり理解しておきましょう。
業務委託することで採用・育成コストを抑えられたりコア業務に専念できたりする点はメリットですが、契約先は慎重に選ぶ必要がある、質が低下する可能性があるなど注意点もあります。その点はしっかりと認識しておくことが必要です。
また、業務委託契約には契約書が必須となるため、今回紹介した項目をきちんと明記し取引を行いましょう。
Adeccoでは、上記のような人事ノウハウをわかりやすくまとめ、定期的に更新しております。
メールマガジンにご登録いただくと、労働法制や人事トレンドなどの最新お役立ち情報をチェックいただけます。
最新の人事お役立ち情報を受け取る(無料)