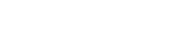人材派遣の仕組み全体を規定する「労働者派遣法」はたびたび法改正されています。
労働者派遣法の改正内容を把握せずに、派遣社員を受け入れていると知らないうちに違法行為をしてしまうリスクが生じるため、人材派遣を活用する場合には最新の法律を把握しておきましょう。
本記事では労働者派遣法とは何か、派遣される人材の雇用形態や人事担当者が法改正で注意したいポイントなどを解説します。
労働者派遣法とは?
労働者派遣法の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」で、2012年10月1日に従来の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から改称されました。
労働者派遣法の主な目的は「派遣労働者の保護」で、2012年に法律名が改称され、法律名にも「派遣労働者の保護」が明記されたことで、名実ともに派遣労働者の保護を目的とした法律となりました。
労働者派遣法制定の目的
労働者派遣法は「雇用形態を問わない公正な待遇の確保」を目的に1986年に制定されました。
労働者派遣法制定以前の日本では、労働者派遣は長らく禁止されていました。
しかし、派遣事業の類似業務を行う企業の存在や日本社会の経済成長に伴う人材不足に対応するため、労働者派遣法が制定し派遣事業が解禁されました。
労働者派遣法は、1986年の制定以降、経済の変化や働き方の多様化に対応するために何度も改正が行われており、2020年施行された改正労働者派遣法が現行法です。
参考・出典:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
参考・出典:厚生労働省「労働者派遣法の改正について」
派遣される社員の雇用形態
派遣される社員は、派遣元企業との間に雇用契約を結びますが、雇用形態には「有期雇用派遣」「無期雇用派遣」「紹介予定派遣」の3つが存在します。
有期雇用派遣
有期雇用は、雇用期間が定められた雇用形態です。
雇用期間は、雇用主である派遣元企業と派遣社員の間で設定され、一般的には3ヶ月、6ヶ月、1年などの単位で雇用期間が定められます。状況によって、有期雇用契約が更新されないケースもあります。
無期雇用派遣
無期雇用は、雇用期間の定めがない雇用形態で定年までの勤務が可能です。有期雇用と異なり、長期的に安定的な働き方が可能で将来的なキャリア形成も可能です。
紹介予定派遣
紹介予定派遣は、派遣先企業で一定期間勤務した後に直接雇用に切り替えが予定された人材派遣です。
派遣期間中に、派遣された人材と派遣先企業の双方がお互いの適性を見極められるため、採用後の安定的かつ長期的な雇用が見込めます。
なお、紹介予定派遣での派遣期間は最長6ヶ月です。
労働者派遣法の歴史
日本の人材派遣の歴史は1986年の労働者派遣法の制定からはじまります。後に、3回に渡る大きな改正を経て、2020年に改正労働者派遣法が施行され現在に至ります。
労働者派遣法の制定から現在までの変遷を学び、法律の目的や意義の理解を深めましょう。
1986年〜2000年:労働者派遣法の制定から紹介予定派遣の解禁まで
日本ではかつて、第三者による人材派遣はあっせんと呼ばれ、紹介者による賃金の中抜きが問題視され禁じられていました。
ところが、経済成長に伴う人手不足を背景に、企業から人材派遣解禁のニーズが高まった結果、1986年に労働者派遣法が施行され、人材派遣の歴史がスタートします。
後に労働者派遣法の改正が繰り替えされ、人材派遣の対象業種や形態も変化しました。
- 1986年:法律施行によって13業務のみ派遣が解禁、同年中に16業務に拡大
- 1996年:バブル崩壊の影響から人材派遣のニーズが増加し対象が26業務に拡大
- 1999年:規制緩和が進み対象業務は原則自由になり、反対に禁止業務が定められる
- 2000年:紹介予定派遣が解禁される
2004年〜2007年:製造業務への派遣解禁、期間延長
2000年代に入ると、人材派遣の対象業務がさらに拡大し、派遣期間も延長されます。
- 2004年:製造業への派遣が解禁され、専門26業務への派遣期間は無制限になる
- 2006年:医療領域の一部業務の派遣が解禁される
- 2007年:製造業への派遣期間が最長1年から3年まで延長される
2012年〜2015年:規制強化や3年ルール見直し
人材派遣が解禁されて20年以上が経過し、派遣労働者の処遇や待遇が社会的な問題となり2012年と2015年に派遣法の改正が実施されます。
- 2012年:派遣法が改正され日雇い派遣が原則禁止となり、待遇強化などが行われる
- 2015年:派遣法が改正され3年ルールの期間制限が見直される
2020年:同一労働同一賃金
2020年の改正での大きな目的のひとつが「同一労働同一賃金」の徹底です。人材派遣の解禁から30年以上が経過して派遣労働が定着するなかで、正社員と派遣労働者の賃金格差が問題視されていました。
そうしたなかで同一労働同一賃金は、派遣先企業で正社員と派遣社員の間の不合理な待遇差の解消を目指し、掲げられました。
同じ仕事をしているにも関わらず正社員と派遣社員では賃金に大きな差が生じている状況を改善するために同一労働同一賃金がスタートしました。
2021年:派遣労働者への説明義務強化
2020年に施行された改正労働者派遣法で掲げられた「同一労働同一賃金」を促進するために、翌年の2021年には派遣先企業に対して、待遇に関する情報提供が義務化されました。
派遣元企業に事前提示される情報には、派遣先企業で担当予定の業務内容や同じ業務を担当する派遣先企業の正社員の待遇などが含まれ、同一労働同一賃金の徹底を目的とした改正です。
労働者派遣法で注意するポイント
人材派遣を受け入れている企業や人材派遣事業に関わる企業にとって、労働者派遣法の正しい理解と遵守は欠かせないため、数年ごとに改正される労働者派遣法のキャッチアップは重要です。
人材派遣を正しく活用する上で、人事担当者が注意すべき労働者派遣法のポイントを解説します。
日雇派遣、二重派遣は禁止
労働者派遣法では、日雇派遣と二重派遣を禁止しています。
日雇派遣とは、派遣期間が30日以内に定められた短期間の派遣です。労働者派遣法では、派遣期間は最短31日以上と定められていて、30日以内の派遣は日雇派遣とみなされて原則禁止されています。
また、派遣先企業が受け入れた派遣社員を別の企業に派遣する二重派遣も禁止されています。
同一労働同一賃金に留意する
2020年に施行された改正労働者派遣法により「同一労働同一賃金」が原則です。
同一労働同一賃金では、派遣社員と派遣先企業の直接雇用社員が同じ業務に従事する場合、両者の待遇は同一でなければなりません。
派遣社員の給与は、派遣元企業から支給されるため、派遣元企業は派遣先企業から派遣社員が対応予定の業務内容や同じ業務を担当する派遣先企業の社員の待遇条件の確認が必要です。
受け入れ時の派遣者特定は禁止
人材派遣を利用する企業が、派遣元企業に対して派遣する人材を特定する行為は禁止されています。
派遣先企業による派遣される人材の特定行為には、派遣契約締結前の面接や履歴書などの提出、特定の年齢層の人材に限定した派遣依頼、性別の限定などです。
派遣される人材の雇用主は派遣元企業で、派遣先企業とは雇用関係がないため、面接や書類による選考を行う権利がありません。
派遣先企業の人事担当者は、派遣元企業と遣り取りのなかで、特定行為と見なされるリスクがある行為に注意が必要です。
有期雇用派遣の契約上限は3年
派遣元との雇用契約が有期雇用の派遣社員は、同一事業所の同一部署での派遣期間が原則最長3年と規定されています。
派遣先企業が、同一事業所で3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣可能期間が終了する1ヶ月前までに、事業所の過半数労働組合などから意見聴取の手続きが必要です。
意見聴取では、過半数労働組合などに対して「労働者派遣を受け入れる事業所や派遣就業の場所」と「延長しようとする派遣受け入れ期間」を書面で通知します。
有期雇用派遣者への安定雇用措置
派遣元企業は、有期雇用の派遣社員が派遣先での就業期間の3年以降も継続就業を希望する場合に、以下の安定雇用措置が求められます。
- 派遣先企業への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供
- 派遣元企業での無期雇用への切り替え
- 有給の教育訓練受講や紹介予定派遣の提供など安定雇用の継続を図るために必要な措置
離職後1年以内の労働者は派遣受け入れ禁止
派遣先企業は、自社を離職して1年以内の元社員を派遣社員として受け入れられません。同様に、派遣元企業も派遣先企業を1年以内に離職した元社員を派遣先企業に派遣できません。
派遣先企業は、派遣元企業から(自社)離職後1年以内の元社員の情報提示された場合は、禁止規定に抵触する旨を派遣元企業に通知する必要があります。
期間制限(抵触日)に留意する
人材派遣を受け入れる際に注意すべき点が、受け入れ期限制限ルールです。特に「抵触日」と呼ばれる「派遣を行ってはいけない日」の存在を理解しておきましょう。
人材派遣の抵触日とは
「抵触日」とは、派遣可能期間の満了日の翌日に設定される派遣が禁止されている日です。
たとえば、2024年2月1日に派遣社員を受け入れた場合、派遣期間の満了日は2027年1月31日となり、抵触日は翌日の2027年2月1日です。
抵触日と派遣可能期間は連動しており、派遣可能期間には事業所単位と個人単位2つの期間制限があるため、抵触日も事業所単位と個人単位で異なります。
事業所抵触日
事業所単位の期間制限では、原則として同一の事業所にて3年を超えて派遣を受け入れることはできません。
事業所内に複数の部署があり、派遣社員が複数名在籍する場合は部署に関わらず、最初に派遣社員を受け入れた日が、事業所単位での派遣受け入れの開始日で、3年経過時点で派遣可能期間が満了します。
事業所単位の抵触日は、上記の事業所単位での派遣可能期間満了日の翌日です。
派遣社員を複数部署で複数名受け入れている企業では、最初に受け入れた派遣社員の派遣可能期間によって事業所全体の抵触日が設定されるため、派遣社員の派遣期間とは別に管理が必要です。
しかし、事業所では派遣可能期間の延長手続きが可能で、期間延長が成立すれば抵触日の影響もなくなるので、事業所単位の派遣可能期間と抵触日を明確にし、必要な手続きを進めましょう。
個人抵触日
派遣可能期間は、事業所単位とは別に派遣社員の個人単位でも存在します。労働者派遣法では、同じ派遣労働者は3年を超えて同一の組織単位にて派遣を受け入れることはできないと規定されています。個人単位の3年は、派遣元が変更されている場合も通算されます。
派遣社員の個人単位では、同一組織で3年以上の派遣勤務はできませんが、同じ会社の別組織なら勤務可能です。
派遣可能期間と同様に、抵触日も個人単位で設定され、派遣可能期間満了日の翌日が抵触日です。
個人の場合、3年を超えて同一組織での派遣勤務が禁じられているため、抵触日を迎えた場合は「同じ会社の別組織への異動」「派遣先企業での直接雇用への切り替え」「別企業への派遣」「派遣元企業での無期雇用への切り替え」などが必要です。
無期雇用と60歳以上の派遣労働者は期間制限の対象外
派遣可能期間の制限は、派遣元企業との雇用契約が有期雇用の派遣社員が対象です。
派遣元企業で無期雇用契約の派遣社員や60歳以上の派遣社員には、派遣可能期間の制限がなく、抵触日もありません。
労働者派遣法を違反すると罰則や行政処分の恐れがある
労働者派遣法に違反した場合、派遣元企業と派遣先企業の両社ともに事業廃止命令や事業停止命令などの行政処分を受けるリスクがあります。
たとえば、人材派遣の事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要ですが、許可を得ずに無許可で派遣事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
また、派遣可能期間の制限を超えて派遣を行うと30万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
労働者派遣法は、1986年に制定された派遣労働者の保護を目的とした法律です。労働者派遣法は、1986年の施行から現在に至るまで複数回の改正を重ねています。
改正の内容は、常に派遣労働者の処遇と待遇の改善を目的とし、日本の人材派遣サービスの発展に寄与してきました。日本では、少子高齢化の影響による人材不足が深刻で、人材派遣のニーズは増加しています。
人材派遣が適切に発展し続けるためには、派遣元企業と派遣先企業の双方が、労働者派遣法を正しく理解した上での適切な人材派遣の活用が求められます。
アデコでは、人材派遣事業を展開しており、有期雇用派遣から無期雇用派遣まで課題に応じてさまざまなサービスを提供しています。
アデコの人材派遣サービス
人材に関するさまざまなお悩みや課題を、アデコの人材派遣が解決します。アデコの人材派遣サービスを活用いただくメリットは以下の3点です。- メリット1:人材の安定確保
- メリット2:課題に対応した派遣形態
- メリット3:パフォーマンス最大化
在籍している派遣社員は34,000名以上と、さまざまなニーズに応える確かな人材供給力を有しています。また、全国に40以上の拠点を展開しているので、きめ細やかな対応が可能です。テレワーク派遣にも対応しており場所にとらわれない人材も紹介します。
さらに、人材に関する様々なテーマを取り上げた無料セミナーを多く開催しています。セミナーでは、労務管理や組織開発、人材育成などをテーマに、日々の人事業務や企業の人材戦略に活かせる情報発信を行っています。
人材派遣の検討や人事関連のお悩みがございましたら是非ご参考にしてください。
監修いただいた専門家
Profile

大学院時代には労働法を専門的に学び、弁護士となる。2015年にリフト法律事務所を立ち上げ、IT法務、企業のサポートに注力している。法律、労務に関する知識に加え、IT関連の知識、コーチングの知識を活かし、全国にある多数の企業の顧問弁護士として日々サポートをしている。また、一般社団法人弁護士業務デジタル化推進協会(LPDX)の理事でもあり、上場企業をはじめ各種研修・セミナーの講師を勤めている。