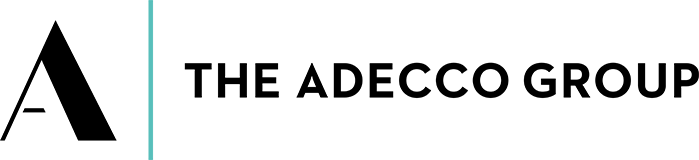あると思います。1980年代から90年代に生まれたいわゆるミレニアル世代の従業員は、それ以前の世代と比べてモチベーションのあり方が大きく変わっています。以前の世代は、目標を達成し評価されることがインセンティブとなり、それによってモチベーションが向上するという傾向がありました。これは「外発的動機づけ」と呼ばれるものです。それに対して、ミレニアル世代は「内発的動機づけ」を重視する傾向があります。
2016年、ATD(Association for Talent Development)の国際カンファレンスで発表された調査結果によれば、ミレニアル世代にとって「お金」「自由度」「名声」といった要素はあまりモチベーションを向上させる要因にはなりません。むしろ、その仕事に「世の中を良くできる」「自分の成長につながる」「家族や家族のように大事な人のためになる」といった意味を見出すことがモチベーションの大きな要因となることがわかりました。評価とインセンティブを重視する従来のパフォーマンスマネジメントが若い従業員のマインドとうまく適合しなくなっているのです。